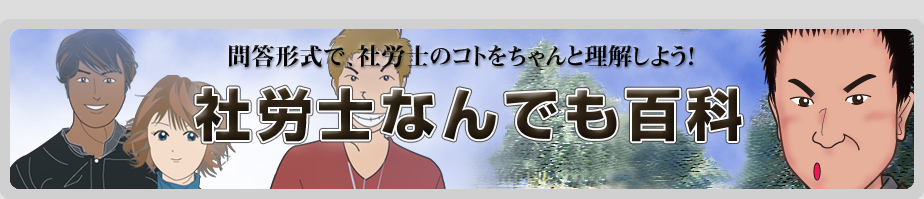大学の勉強って関係ある?<法学部編>
 |
先生、私たち大学生が社労士の勉強をするのに、大学の勉強で試験勉強に直接関係することってあるんですか? |
|---|---|
 |
うん。そうか、みんな大学生だもんね。大学では何学部に所属しているの? |
 |
私は、法学部です。 |
 |
僕は、経済学部です。 |
 |
俺は、経営学部やで~ |
 |
よし、じゃあ、学部ごとに、どういった内容が役に立つのか、話そう。まずは、法学部から!リナは法学部でどんな法律を中心に勉強しているんだ?『労働法』って学習してる? |
 |
えっと、今は民法を中心にやっています。労働法は、うちの大学では3回生以上じゃないと履修できないんです。 |
 |
社労士の試験には、『労働法』を学習していることは、もちろん有利なんだ。しかし、多くの大学のカリキュラムでは、労働法を半年、もしくは1年間学習しても、社労士の試験で必要な範囲でいうと、(択一式で)3問出題されるかどうか、くらいの分量だと思っていいかもしれないな。リナの大学のカリキュラムで、『労働法』は何単位あるんだ? |
 |
『労働法』は・・・『総論』・『各論』の2つですね。1つが2単位だから・・・合計で4単位ですね。『総論』は「労働組合法」、『各論』は「労働基準法」となっているみたいです。 |
 |
法学部では「法律の知識」を勉強するというより、「法律の解釈のしかた」を勉強するので、試験に必要な知識よりももっと深い内容、判例研究などをやるでしょ。だから、大学の勉強は社労士として独立開業するときは、非常に役に立つと思う。でも、社労士の試験では、「知識」を求められるんだ。出題されるものによっては、「法律の解釈」で解決できるものもあるから、有利な点ももちろんあるが、法学部に多少染まっていると、法律の解釈をしすぎて、単純な問題を深読みしてしまうこともある。気をつけてね! |
 |
法学部だから、有利だと思っていいワケではないのか・・・ 落とし穴があるんですね・・・ |
 |
ま、法律用語など、勉強を始めた一般のヒトに比べると、法学部出身者のほうがとっつきやすい点は、非常に有利だね。「法学部はツブシがきく」なんて言われやすいが、司法試験だけじゃなくて、目指せる資格に幅が広いのが有利だ。 |
| <関連記事> |
|