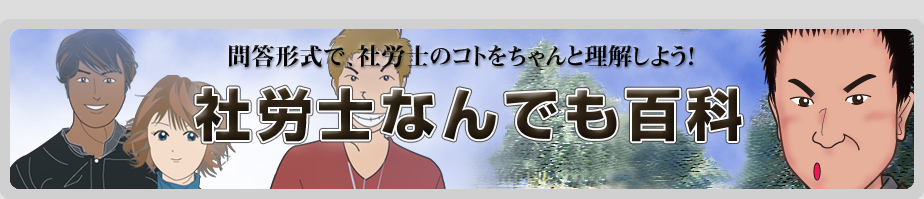社労士六法というのは?
 |
先生、『社労士六法』ってものがあるって聞いたんですが。 |
|---|---|
 |
ヒロシくん、本屋さんなどで、『六法全書』というのを目にしたことはない?法律の条文を1冊にまとめた本、言い換えたら「辞典」のことよ。 |
 |
さすがリナだね。じゃあ、なぜ「六法」なのか知っているかな? |
 |
えっ、わかりません。なぜなんですか? |
 |
うん。従来から、日本における主要とされる法律が「憲法」・「民法」・「刑法」・「商法」・「民事訴訟法」・「刑事訴訟法」の6つであったことから、この6つの法律を載せた「六法」の「辞典」、それが『六法全書』と呼ばれてきたんだ。 |
 |
そういえば、法学部の先生がそんなことを言っていたわ。 |
 |
ははは。先生も、よくそんなことを言っているよね。法学部の学生は、それだけ法律を大切にしろ、ってことだよね~。だけど、日本の法律ってたった「6つ」ではないよね。それに、社労士にとって試験で出題される重要な法律は「労働基準法」「労働安全衛生法」「労働者災害補償保険法」「雇用保険法」「労働保険料の徴収等に関する法律」「健康保険法」「厚生年金保険法」「国民年金法」・・・ |
 |
あれっ、すでに9つもありますよね・・・ |
 |
そう疑問に思うよね。ヒロシがさっき言っていた『社労士六法』だけど、社会保険労務士が仕事上、使うための法律辞典には、『六法全書』の名前を借りて『社会保険労務六法』という法令集があるんだ。『六法』という言葉はいまや、「6つ」という数字を示すのではなく、『法令集』という意味をもった言葉として認識がされているんだよ。 |
 |
じゃあ、『社労士六法』にはいくつの法律が載っているんや? |
 |
実際に社労士六法に載っている法律を数えてみたら、50以上はあるよ。しかも、日本の立法機関である国会により、毎年新しく法律が制定されるから、これからも増えていくだろうね。 |
 |
ぎゃー!!50以上も!!そんなに法律を勉強しないといけないのか・・・ |
 |
ははは。安心していいよ。ほとんどのヒトは、勉強を始めるときにはまずそういった不安になるだろうね。だけどはっきりいって、「必要な法律だけを覚えれば大丈夫」なんだ。登録して仕事をバリバリされている社労士の先生でも、試験に合格したから、それで社労士になっているんだから、全部の法律を覚えている先生なんていないんじゃないかな。逆を言えば、社労士になるために最低限必要な知識は、社労士試験で聞かれている、のだから、まずは社労士試験に出題される内容だけ理解できれば十分だ!試験に出題されないような法律を知っている社労士の先生は、よっぽどマニアックな先生だろうね・・・ |
 |
しかし、そんなに法律があっても、知っていなくてもいいんかいな? |
 |
仕事上、知らない法律が出てきたときに調べることができるよう『社労士六法』があるんだ。『社労士六法』を全部覚えている!てヒトがいるなら、ぜひ会ってみたいもんだね。その記憶力を讃えて金メダルをあげてもいいくらい、社労士に関する法律は多いんだ。 |
 |
じゃあ、困ったら『社労士六法』を見ればいいから、法学部じゃない僕でも助かりますね~ |
 |
そうだね。だけど社労士として仕事する上で、「法律ではどう決まっているのかな?」と疑問に思って調べるとき、もちろん、法律の条文そのままを読むことになるぞ。難しい文章のため、読んでて意味が分からないものもあるだろう。社労士は法律家なのだから、やはり法律を読んで理解できるチカラはつけておいたほうがいいね。あっ、試験には『社労士六法』は持ち込むことはできないから、注意が必要だよ!! |
| <関連記事>
|
|