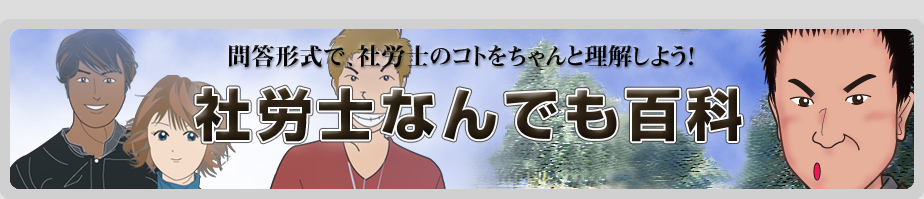社労士資格の歴史
 |
先生、社労士は2008年に「40周年」を迎えた、って新聞に書いてあったけど、社労士の歴史について教えてください!どうしてこの仕事ができたんだろう? |
|---|---|
 |
じゃあ、歴史的な背景から見てみよう。戦後、労働者の権利を法律によって守るために、いわゆる労働三法(「労働関係調整法」(1946年)・「労働基準法」(1947年)・「労働組合法」(1949年)が制定されたんだ。これまで、労働者を法律で保護する、という背景はなかったんだ。 |
 |
あっ、『労働三法』って聞いたことあります!中学校の社会科で習った気がします。 |
 |
そう。法律によって労働者の権利が確立されたことと、さらに日本の経済成長とが相まったため、労使間の対立、例えばストライキの頻発といった問題が生まれた。やはり、法律で守ってもらえるなら、これまで弱い立場にあった労働者にも権利意識が出てきた。 |
 |
ストライキか!「交通スト」でバスが動かない、ってことあったで~ |
 |
そうだよね。「労働者の権利」も重要だけど、毎日ストなんかされたら利用者にとっては不便だし、会社も商売あがったり、だよね。 |
 |
それが、社労士、なんですね!! |
 |
この頃は法律上、書類の代行などは「行政書士」という士業があったんだけど、より専門的な資格として「社会保険労務士」を1968年「社会保険労務士法」が議員立法により制定された。制度発足による経過措置として、当時の行政書士には特認として、試験を受けなくても社労士資格をもつことが認められた。当時、行政書士から社労士になった者は約9,000人なんだって。また、1980年8月末の時点で現に行政書士であった者については、社労士の独占業務に関わる書類の作成および使者として提出することが認められたが、提出代行及び事務代理、あっせん代理は禁止されたんだ。 |
 |
じゃあ、その頃に行政書士だった人は得だったんですね。 |
 |
まあ、それはあくまでも例外だからね。今では、社労士になろうと思ったらちゃんと試験に合格しなければならないよ。今では、行政書士と社労士は、全く専門分野が違うからね。そして2008年、社労士は40周年を迎えた、というわけなんだ。 |
 |
へーっ、40周年、の歴史にはそういった経緯があるんですね。これからの社労士はどうなんでしょうか? |
 |
2007年4月、司法制度改革において、新たなADR(Alternative Dispute |
| <関連記事>
|
|