テキスト本文の開始
(2) 調整しない場合 (2項)

調整対象期間の各月について、次のいずれかに該当する月があったときは、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない(支給停止しない)。
イ) その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日*1及びこれに準ずる日として政令で定める日*2がないこと。(平16択)(平20択)(平10記) |
ロ) その月の分の老齢厚生年金について、在職老齢年金の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
|
|

□*1「基本手当の支給を受けた日とみなされる日」とは、失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の各日をいう(則34条の3)。
□*2「これに準ずる日として政令で定める日」とは、次に掲げる雇用保険法の規定による基本手当を支給しないこととされる期間に属する日とする(令6条の3)。
a) 待期期間であることにより基本手当を支給しない期間(雇用保険法21条)
b) 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと等又は公共職業安定所が行う職業指導を拒否したことにより、基本手当を支給しない期間(雇用保険法32条1項・2項)
c) 離職理由による給付制限により基本手当を支給しない期間
(雇用保険法33条1項)
|

◆「基本手当」との支給調整が行われない場合の考え方
60歳台前半の老齢厚生年金は、原則として、「求職の申込み」をすると支給停止となる。
↓ しかし…
この調整対象期間内においては、実際には基本手当が給付されない期間が含まれることもあり、何ら考慮をしないとすれば受給権者の不利益につながる。
↓ そこで…
「基本手当の支給を受けたとみなされる日」や「これに準ずる日として政令で定める日」が1日もない月については、支給停止は行わない。
↓ ところで…
待期期間や給付制限期間は、雇用保険法において基本手当を給付しないこととしたペナルティー期間であるから、「基本手当が出ないのであれば年金を出す」とすると、雇用保険法の制限趣旨に反することとなる。
↓ したがって…
|
-----------------(130ページ目ここから)------------------
そうした日が月内に1日でもあれば、年金の支給は停止される。
↓ しかしながら…
【具体例】 同じ期間だけ支給停止となったAさんとBさんに不公平はないだろうか?
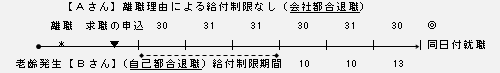 |
a) Aさんは、支給停止期間「6箇月間」で妥当である。
b) Bさんは、6箇月間に33日分の基本手当しか受給しておらず、Aさんと同じ支給停止期間とするのは不合理である。
↓ そこで、Bさんについては…
支給停止期間の調整が行われる(6箇月-33/30(1未満の端数切上げ)=「4箇月」)。
|
|


